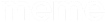【第一弾】
Marylandでの衝撃「当たり前のことを手抜きせずに全力で完遂する」
――MBA留学と米国ラクロス協会インターンを経験した”Joe”さんに聞く、日米スポーツの違い(1/3)
【第二弾】
クラスメイトとのディスカッションから見えた日米における倫理観や価値観の違い
――MBA留学と米国ラクロス協会インターンを経験した”Joe”さんに聞く、日米スポーツの違い(2/3)
【第三弾】
世界トップクラスの「フェイスオフ」。その技術と思考から考察する日本人としての世界における戦い方
――MBA留学と米国ラクロス協会インターンを経験した”Joe”さんに聞く、日米スポーツの違い(3/3)
”Joe”さんに聞く、日米スポーツの違い

Johns Hopkins Universityとの試合後の挨拶
1.Marylandでの衝撃 「当たり前のことを手抜きせずに全力で完遂する」
2018年9月下旬、約1年ぶりに訪れたUniversity of Maryland。私にとって米国の母校である同校が擁する強豪男子ラクロス部を、日本の母校であり自身も学生時代所属した早稲田大学ラクロス部男子が訪れ練習を見学した。卒業生としてアレンジした早稲田ラクロス初の米国遠征では、Johns Hopkins University、U.S. Naval Academy(通称Navy)といったNCAA1部の強豪校とも練習試合を行ったが、早稲田ラクロスの選手たちの多くは「(試合とは異なる観点で)Marylandの練習風景が一番衝撃的だった」と口にしていた。
シーズンイン後すぐの練習だったこともあり、そのメニューは基礎的且つシンプルで、日本でもおなじみの練習ばかりだった。ただ、その質は日本のそれとは全く異なっていた。一切手加減の無いハードコンタクト、選手間の絶え間ないオンフィールドコミュニケーション、ミス発生後のリカバリー、コーチの笛が鳴るまでそんな「当たり前のプレー」に手抜きをする選手は誰一人いない。だからこそ、選手同士がぶつかり合う衝撃、スティックが振り抜かれる音、次のプレーへの移行スピード、これら1つ1つの重みが全く異なっていた。
「当たり前」の積重ねがMarylandを2017年NCAAチャンピオンに導いたことは容易に想像できた。この「当たり前のことを手抜きせずに全力で完遂する」という、ある意味では「美しさ」とも表現できるようなMarylandの姿勢を肌で感じたことは、2018年の早稲田の学生日本一奪還とラクロス全日本選手権(社会人チームも参戦する全国大会)準優勝という結果に少なからぬ影響をもたらしていると思う。では、「当たり前のことを手抜きせずに全力で完遂する」Marylandのような米国の学生スポーツカルチャーはどのように成り立っているのだろうか。
縁あってNCAA強豪校であるUniversity of MarylandのビジネススクールでMBAを学べたことは、日米のビジネスの違いはもちろんのこと、文化・価値観面での違いや、社会におけるスポーツ(特に学生スポーツ)の立ち位置についても考えさせられる非常に良い機会だったので、この場を借りて私見を述べてみたい。
【 I スポーツについて】
2.日米の学生アスリートの差 「マルチタスク管理能力」
①盲目的にスポーツに没頭しがちな日本の学生アスリート (特別扱いされがちな体育会)
私個人の感覚だが、日米の学生アスリートの間にはマルチタスク管理能力の面で大きな隔たりがあると思う。自分自身の大学時代の学生生活を振り返ると、所属する体育会ラクロス部の活動が4年間の中心にあった。(少なくとも名目上は)本分である大学の講義や課題は、部活動よりも明らかに優先順位が低かったし、正直なところ出席点だけもらってあとは寝るだけ、という講義もあったように記憶している。ゼミの友人と仲が良かった私は、彼らと会うのが楽しくてグランドから45分離れたキャンパスに毎日のように通っていたが、思い出すのは講義内容よりもバカ話をして笑った思い出ばかりだ。学生アスリートの中には、講義をサボって1日中練習だけしている人がいたようにも聞いたし、実際それが「体育会の選手だから」という理由で何となく許容される雰囲気もあった。
キャリア形成に関していうと、ラクロス部は就活時期は就活に専念できるルールがあったが、部によっては就活すら認められず監督やコーチが斡旋した企業に就職させられることもあったと聞く。このように、少なくとも10年前の日本の大学では、学生アスリートは大学の中で「スポーツをしにきた人」と扱われ、ある意味では「一般学生とは異なる独特のポジション」に存在していた。2019年現在、この立ち位置がどれほど変化したのかわからないが、少なからず10年前の名残はあるのではないだろうか。
②学業最優先の米国学生アスリート (学業面で特別扱いの一切無い学生アスリート)

毎日ディスカッションした同級生
対して、米国の学生アスリートは学業最優先である。NCAA(全米大学体育協会)の規定で、まず、チームとしての練習時間に制限がある。個人単位で見ても、どれだけ選手として優秀でも、学業成績が伴わなければ、試合はおろか練習にすら参加できない。成績は、出席点程度でクリアできるものではなく、他の学生同様に課題をこなして授業で発言し、フィールドワークもこなして、試験では十分に勉強しなければ取れない水準の点数を取る必要がある。彼らは文字通りアスリートである前に学生なのだ。
NCAA1部のThe George Washington Universityのバスケ部に所属していた渡邊雄太選手(現在NBAとNBA下部組織のNBA G Leagueの両方でプレー)の密着番組でも紹介されていたが、遠征先から深夜・早朝に学校に戻ってきてそのまま授業を受ける、ということもシーズン中には頻繁にあるし、英語が母語でない学生アスリートには英語の補習クラスも半ば義務付けられる。こういう背景もあってか、学生アスリートたち(特に必修授業が多い下級生)は練習後そそくさとクラスに向かう。「体育会の選手」という称号は勉強の手を緩める理由には一切ならない。だからこそ、キャンパス内では体育会の選手たちが真剣に勉強する姿をよく見かけた。
Marylandでは女子のTewaaraton Award(米国大学ラクロスにおける沢村賞のようなもの)を3年連続で獲得した米国女子代表のTaylor Cummings選手(ファイナンスを専攻)が講義棟内のベンチに座ってPCのキャッシュフローモデルと格闘しているのを頻繁に見かけた。また、男子チームの主将を務め、プロリーグであるMajor League Lacrosseで2018年の最優秀ディフェンス選手賞を獲得したMatt Dunn選手(ファイナンス専攻)が授業のトピック(政治経済学的な内容)をクラスの友人とディスカッションしながらコンビニにコーヒーを買いにくる光景も見かけた。これが普通の光景なのだ。キャリア形成に目を転じてみると学生アスリートは充実した卒業生ネットワークという利点を享受できる環境におり、例えばMarylandのラクロス部では卒業生の伝手を使ってシーズンオフのインターンシップも支援しており、スポーツ以外にも目を向ける機会が用意されている。だからこそ、学生アスリートも「スポーツをするため」に大学に来たわけではなく「勉強もスポーツもする、そして人生を切り拓く」ために大学に来たという意識を根底に持っているような印象を受けた。
日本のように「体育会の選手だから」という理由で学業の手を抜くことが許容される雰囲気は一切無い。限られた時間の中で学業・スポーツ両面で結果を出す必要性に迫られていることが、常に「当たり前のことを手抜きせずに全力で完遂する」というカルチャーを構築しているといえるだろう。今年2月に米国からプロラクロス選手2名(大学卒業2年目)が来日し日本の学生ラクロス選手向けにクリニックを開催したが、企業には属さずクリニックを生業の1つにする彼らは夕食前におもむろにPCでエクセルを開き、その場でクリニックの事業収支をはじいて反省点を洗い出し、次のクリニックのプロモーションに関するディスカッションまで行っていた。日本の大学を卒業して2年目の元学生アスリートのうち、何割の人が彼らと同じことをできるだろうか。
3.スポーツにおける観客の存在の意味合いと重み

Johns Hopkins Universityとの試合風景
①米国における観客の位置づけ
スポーツを通じて考えさせられたことがもう1つある。それは観客の存在だ。米国のスポーツを語るうえで、観客の存在は外せない。プロはもちろんのこと、大学や高校のスポーツにも観客が必ず観戦に来るし盛り上がる。それ故、選手としても観客を意識せざるを得ない。学生スポーツにフォーカスすると、「最高の環境」で学生アスリートが「最高のプレー」をし、観客に「最高のプレーを楽しんでもらう」ために学生アスリートと彼ら/彼女らを取り巻く関係者が「厳しさを乗り越える」のが米国流の学生スポーツのストラクチャーだ。そして「最高の環境」での「最高のプレー」が、誰もが楽しめるビジネスチャンスと捉え、学生スポーツに投資を惜しまない文化があるのもまた米国の学生スポーツの華々しさを支える1つの側面でもある。
②日本における観客の位置づけ
一方で日本のスポーツはどうだろうか?NPBやJリーグ、最近ではBリーグやTリーグの登場で、観客が楽しめるような工夫が従来よりも施されるようになってはきたものの、米国の実態と比較すると、観客が楽しめる環境は十分とは言えない。学生スポーツもその部分は同じで、私の知る限りでは、観客を魅了する会場づくりができておらず、学生アスリートたちも観客を魅了することに意識がほとんどないように感じる。(SNSの登場でその意識が向上している印象があるのは良い傾向だと思う。)一足飛びかもしれないが、講義をサボって部活に打ち込む、平日でも1日の生活時間帯のほとんどを練習に費やす、ということが珍しくないような状況に陥ったのは、日本の学生スポーツに観客というポジションが存在してこなかったことが大きな原因の1つであると私は考えている。「試合や練習は学生アスリートやチームのためのもの。勉学を疎かにしてでも学生アスリート自身が納得できていれば問題ない。(観客など)競技の当事者ではない者の目線は気にする必要が無い。」という価値観がどことなく広まり定着しているのではないだろうか。
③スポーツにおける観客の持つ役割
一歩下がって客観的に観客という存在を考えてみると、選手に対して観客が与えるインパクトは大きい。自分自身を振り返っても、出場するラクロスの試合に家族や友人が観戦・応援に来てくれると「良いところを見せたい」という意識が自然と働いた。日常の練習においては、自分自身の他にチームメイトと監督・コーチしか存在しない世界に、いわば「第三者」ともいえる観客が登場することで健全な緊張が生まれる。一方、観客は基本的に試合会場でしか選手を見ないため、試合でのプレーで選手の価値を判断する、というある意味では残酷な目線も持つ。
「○○選手は普段はこれだけの練習量をこなすチームの大黒柱である」というキャプションは、試合でのパフォーマンスが伴わなければ観客にとって何の意味も無い。観客からの声援は選手に勇気を与えパフォーマンスの向上にも繋がる一方で、良いパフォーマンスを発揮できなければ、否応無く批判の目にさらされる。このように、選手にとって観客はストレートなレスポンスをくれる存在だ。この構図を知っているか否かが、そのまま日米の選手の意識に出ているのでは?というのが私の見解である。
米国の学生アスリートは、試合会場で最大のパフォーマンスを発揮することにフォーカスし、時間的・物理的制限のある状況下で日々の鍛錬を積む。パフォーマンスにフォーカスすることで、学生アスリートは自身のスキル習得(Input)のみならず、どうスキルを発揮するか(Output)にもしっかりと目を配るようになる。そう考えると、観客の存在こそがこの好循環を生み出しているともいえる。一方、観客の存在が欠けている日本の学生アスリートは、スキル習得(Input)には長けているものの、どうスキルを発揮するか(Output)という点においては、準備不足の印象がある。
3.「○○道」ではなく「文武両道」 ~二足・三足のわらじを当たり前に~
日本では「野球道」という言葉も存在するように、スポーツにおいても他の何かにおいても「○○道として一意専心に1つのことを貫く」ことを美徳とする風潮があると思う。(語呂的に、「○○道」は「武士道」をもじったものかもしれないが、だとすれば「武士道」はそもそも文武両道を完遂することを掲げており、1つのことだけに取組むのとは正反対。。。)もちろん、何か情熱を注げるものが1つあることは素晴らしいしそれは否定しない。だが、そればかりやっていてはどんどん閉鎖的な世界に入っていくだけだ。講義をサボって練習に明け暮れることで、スポーツのスキルは上がるが人生を生き抜くうえで必要なスキル(勉学・アルバイト・インターンなどで得られるもの)が習得できないかもしれない。どうせならスポーツに必要なスキルも人生に必要なスキルも両方獲得すれば良い。
自分自身の学生時代を思い出すと、卒業後11年経った今でも尊敬して止まないチームメイトは当時から二足・三足のわらじは当たり前に履いていた。選手と併行してラクロス協会学生連盟の運営要職に就きながらマスコミの夏期インターンシップに参加していた先輩は今、日米にまたがる大きな仕事をしているし、中高大と全て同じ部活で過ごした先輩は今、アメリカの名門校でロースクールとMBAをまとめて取得している。そんな魅力的な先輩たちに触発されてか、私自身も同期のチームメイトとともに運営面でラクロス協会をサポートしたし、その経験が社会人になった今でも活きている実感はある。マルチタスク環境下での納期管理、優先順位づけ、情報共有先の抽出と共有の頻度の検証、それに基づいてトライ&エラーを繰返し何度もPDCAを回してみる、など学生アスリートとしてはなかなかできない経験を学生時代にさせてもらった。
2000年代日本のラクロスは環境として、選手自身がチームや協会運営で何かしらの役割を担わなければ回らなかったという実情が、却って選手たちに半強制的に「二足のわらじ」を求め、それが故に超回復的に物事をこなす力が養われたのかもしれない。また、私個人は幸いにもアカデミックな分野で良い出会いもあった。近年、SNSの登場でセグメント同士の信頼関係やそのマネジメントについて急激に重要性が上がっているが、Public Relationsという授業に出会い、そういった課題について20歳そこそこからじっくりと学ぶことができた。また、後述する「倫理観」についても十分に考えさせられた。20歳そこそこの学生アスリートとしてこの授業を受講できたことは、社会で起こっている物事の見方を変えてくれたし、私自身の7年後のMBAに繋がったことは間違いない。
Marylandでの生活を通じて米国の学生アスリートたちが置かれた環境を理解するにつれ、どことなく懐かしさというか共感を感じるようになったのは、彼らも私同様に「二足のわらじ」を半強制的に履いた結果、自分自身の抱えるマルチタスクを管理する能力を磨いたからなのかもしれない。彼らは口々に「It’s all about time management. It’s tough, but you’ll manage to do whole the stuff.(全てはタイムマネジメントだよ。難しいけど、やってみれば全てできるようになる。)」と言っていたが、その言葉はマルチタスクを乗り越えたものにしか出せない言葉であり、同じ言葉を1人でも多くの日本の学生アスリートが自信を持って口にできる日が来て欲しいと願っている。
(つづく)