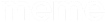加納慎太郎 2016年ヤフー株式会社 入社
2020年に向けて、戦い続ける男がいる。
状態を表すのであれば、立つという言葉はふさわしくないだろうか。
なぜなら座っているのだから。
加納慎太郎は立ち向かっていた。加納慎太郎は、前進もしなければ後退もしない。
その与えられた場所で戦う。同じ場所で戦う。
前に進むことはできないけれど、目の前の敵から目を離すことはない。それが車いすフェンシングの戦いだ。
車いすをピストと呼ばれる台に固定する。
対峙する二人の選手は、盤面に置かれたナイトのようで、動き出す瞬間を待ち構えている。
主審が選手に確認をする。
「プレ?」用意はいいか? という意味の言葉にうなずく。
「アレ!」主審の声が、始まりの合図が鳴り響く。
車いすフェンシングの試合が始まった。
真っすぐに突いてくる相手に対して退くことは許されない。
車いすが固定されているため、下がることはできない。
攻撃を避けようと自らの剣でいなす。
それと同時に相手への攻撃と転じる。
後退もできなければ前進もできないため、身体が前に傾いていく。
騎兵が馬を操るように、左手で車いすを握り不安定な身体を支え攻撃を可能にする。
胸への一撃。
「ピーッ」という電子音が鳴り響いた。
車いすフェンシングの試合は、一瞬の駆け引きの連続だ。
相手より先に攻撃を成功させようと、気持ちが前のめりになる。
前へ。前へ。前へ。
決して前進することのできない競技なのに、目の前への意識が高まっていく。
決して前進することのできない競技だからこそ、目の前の勝利が輝いているのか。
加納慎太郎は前へ進むための脚を失ったのに、誰よりも前を見つめている。
それは2002年、16歳のときだった。

寒さにはもう慣れている2月、それでもバイクに乗るとやはり寒く感じる。
3月生まれだから、もうすぐ17歳になる。
加納はそのときの誕生日を、そのときの春を、
かけがえのない青春を、病室で迎えた。
夏も、秋も冬も。さらにもう一周
季節が巡るほどの時間を病院で過ごした。
交通事故で左脚を失ってしまったのだ。
もう二度と自分の脚で歩くことはできないのだろうか。
事故により失ったものの悲しみは、決して小さなものではない。
誰もが気の毒に思ったことだろう。
しかし、すぐに前を向き直していた。
立ち上がることができた。
左脚は失ったけれど、義足を手に入れたのだ。
リハビリの末、10年後には子供の頃から打ち込んでいた剣道にまた打ち込めるようになる。
「いつか見とけよ」とマイナス方向へ進むはずのエネルギーが、
後退することなくその場所に溜まり続け、前進する力へと爆発した。
巨大なバネがきりきりと音を立てて縮むように、初めから前に飛び出していくことは自分で分かっていた。
前を向いてさえいれば、どんなに後ろへ身体が引っ張られても、
いつか必ず前進するエネルギーに変わる。
事故で左脚を失ったからといって、この世で自分が最も不幸を浴びている存在だなんてことはない。
強くなりたかった。
義足での剣道は、思うようにいかないようなこともある。
子供の頃は地元の強豪チームで、レギュラーを張るほどの実力だったことを思い出す。
今は得意だった足さばきを中々再現できずにいる。
あの頃は地元のチームでレギュラーだったけれど、そこで満足しなかった。
全国には自分より強い選手がたくさんいて、上を知るたびに強くなりたいと思った。
己の中にある剣を研ぎ続けていた。
剣道で負けると悔しい。
その気持ちは自分がどんな状況に置かれても変わらない。
悔しい。
自分を磨いていたときと同じ気持ちを抱き続けている。
そして悔しいなら、何とかしなくちゃいけない。
健常者に勝つにはどうしたらいいのだろうと前を見つめる。
自分の弱点はこの義足。
それなら話は明快だ。
義足は左脚を失った証明なんかじゃない。
弱点にならない義足を作ればいい。
十分な性能を発揮できるように整備すればいい。自分をもっと鋭く、薄く、
そして強く変えてくれるもののはずだ。
それがあっても勝てるはず。
それがあるから勝てるはず。
そして加納は義肢装具学校に通い始めた。
2013年夏。左脚を失ったあの日から、何度冬を越えたのかだろうか。
数え直さなければ分からないほどの時が過ぎ去った。
義肢装具学校の研修で沖縄に来ていた加納に、東京パラリンピック開催の知らせが届く。
健常者に剣道で勝とうとしていた加納にとって、それは待ち構えていたものではない。
しかし、その知らせが急に夢のような話に思えてきた。
華やかな舞台に立つことができる。
力強い足跡を残すことができる。
たとえ左脚がなくても、失ったからこそ、強い自分になれると思えるようになった。
その中で車いすフェンシングを選んだのは、大好きだった剣道の技術を生かせると思ったからだ。
同じように剣を使用するスポーツであれば、過去の経験も生かすことができるはず。
行動に迷いはなかった。
九州で車いすフェンシングができる場所はなく、導き出された場所は京都。
加納慎太郎は車いすフェンシングに出会った。
それまでの人生と、それからの人生。
どちらの困難が多かったかなんて考える必要はない。
今、目の前にいるものに立ち向かっていくだけだ。
だけど、加納慎太郎は、車いすに座って、目の前の敵と戦うことを選んだ。
剣道の経験が生かせるように、剣を使用する競技を探して見つかったのが車いすフェンシング。
簡単に競技成績を残せたわけじゃない。
剣道では前後の足さばきで間合いを取っていた。
その感覚がまったく通用しない。
ピストに固定された車いすは、退くことが許されない。
勝負は一瞬で決まってしまう。
日本国内では車いすフェンシングの存在はほとんど知られていない。
文化として根付いているヨーロッパとは違い、競技者が少ない。練習機材がない。
技術を教えてくれるコーチがいない。
たくさんの「ない」ことばかりが積み重なる。
少ない情報で戦わなければならない。
それでも加納は車いすフェンシングを辞めなかった。
そんなことを思うことすらない。
試合中、車いすが固定されているように、退いて諦めることはできない。
考えにも及ばなかった。
目の前にあるのは東京パラリンピックという、大きな夢。
目の前に見えているものから、視線を逸らさずにいられるはずがなかった。
ずっと前を見ていると、ずっと向こうにも道が続いていることに気がついた。
この先はどうなっているのだろう。誰かの足跡はどこにもない。
2016年、加納慎太郎はヤフー株式会社に入社する。
車いすフェンシングで戦う障がい者アスリートとして、
それだけではない、一人の社員として働くことを決意した。
入社を熱望した理由は自分自身を甘やかさない環境にあった。
加納と同じように車いすフェンシングで戦う選手の中には、一日練習に専念できる環境を持つ者もいる。
加納が仕事をしている時間にも練習に励んでいる。
加納はそれを選ばなかった。
午前中に仕事をして、練習は午後から。
入社当初は練習の合間に、慣れないIT用語を覚え、タイピングを練習し、先輩から借りた本を読み、たくさんのことを吸収した。
できないことばかりが目立って、申し訳ない気持ちがずっと続いている。
仕事の上でのスキルと、車いすフェンシングのスキルには関係はないかもしれない。
はっきりと、ないと言ってもいい。
それでもやると決めたのだから、見つめるのは前だけでいい。
できないことを振り返る必要なんてない。できないことがあるのなら踏み倒していけばいい。
申し訳なく思って辞めるんじゃなくて、新しい力になればいい。
ヤフー株式会社も加納を甘やかさない。
社員の一人として、他の社員と一体なんの違いがあるというのか。
仕事を割り振り、仲間としてともに会社を支える。
仲間として競技を応援する。別に、加納だから特別なんじゃない。
アスリートだから特別なんじゃない。
障がい者だから特別なんじゃない。
社員6000人の中の大切な仲間の一人だから特別な存在なんだ。
社員にはそれぞれの事情があって、それぞれの働き方がある。
その中のひとつとして加納は戦っているのだ。
車いすフェンシングの試合で、相手選手・チームからの抗議を受けるようになった。
それまでの日本は車いすフェンシングの最前線を追いかける立場だ。
今も立ち位置は変わらない。
前を走る海外の強豪国の視界に入ることもなく、姿を見られることもなかった。
日本が相手ならどうせ勝つだろうと、レギュレーションに対して抗議を受けることはなかった。
入社後にも、めきめきと力をつけていった加納は警戒されるようになる。
トップを走るマラソン選手が、後ろを振り返るように、その存在が脅威へと変わっていく。
それまで聞こえないはずの足音が大きくなっていく。
どれほど近づいたのだろうかと、確認されるようになる。
ゴールは前にしかないのだから、後ろを見る必要はないのに。
どれだけ相手に意識されようと試合に勝てばいい。
むしろ、警戒されることそれ自体が
勝利に近づいていく確信へと変わっていった。
仕事だって同じだ。
ひたすら追いかけなければ、追い越そうとしなければ、誰にもその姿は見られない。
他の社員より、働く時間は短いけれど必ず意識させてやる。
できないことばかりで、追いかけることしかできないけれど、必ず追いついて、ずっと前にいる人の背中をこの手で押してみせる。
入社して一年が過ぎても、前を見ることだけは変わらずに続けてきた。
仕事をすることで、車いすフェンシングの練習をする時間は限られるようになった。
それでも競技成績は上向いている。だからこそ、かもしれない。
仕事を人より早く終えて練習をする。
人がデスクと直面している、働いている、汗をかいている中で、練習に集中する。
業務を頑張って、競技も頑張って、限られた時間の中だからこそ、
見えてくるものがある。感じる思いがある。
その気持ちを力に。その時間を濃密に。
ピストに固定された車いすの上で前を向くエネルギーに変える。
変え続けている。
2020年へ
東京で加納は目の前に立ちはだかる大きな敵と戦うだろう。
それまでに、どんな道を、自分の意志で、自分の脚で歩んでいくのだろうか。
加納が歩んでいるその先に、選んでいるその道に、足跡なんてどこにもなかった。
前を見て、地面を踏む。
その力が反発して前進する力へと変わる。
その力が強ければ強いほど、足跡が強く残る。
車いすフェンシングで戦う加納は、ヤフー株式会社で働く加納は、その足跡を辿って後戻りをすることなんてなかった。
だから、どれだけ強く足跡を残してきたのかをまだ知らない。
知る方法もない。
その深い足跡の存在に気づかせてくれるのは、いつかその足跡を辿って追いついてくる、加納慎太郎の姿を追いかける誰かの足音かもしれない。
文・ムコーダマコト