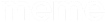現役Jリーガーの井筒陸也(いづつりくや)は、大学時代にサッカー部主将として150人のチームを史上初の4冠に導いた。
誰もが分かるように、この偉業は誰にでもできることではない。では、彼はどうやって成し遂げたのか―。
井筒陸也は考える。
組織を構造的に捉え、主将である自分をもその一部として俯瞰して観察する。
そんな彼だからこそ、150人の部員、一人ひとりに直接ミーティングを行う「1 on 1 meeting」という荒業を考え出し、実行、そしてチームを優勝へ導いた。
井筒陸也は、自分がこれまでにサッカーを経て得た組織と個のマネジメント・ノウハウが、ビジネスの場にも活かせるのではという仮説を立てている。そんな彼の思考に共感し、Meme編集部は今回、「1 on 1 meeting」を行った経緯とその後日談を執筆してもらえることになった。
それでは、井筒陸也の「150人の組織論」を寄稿いただこう。
主将という肩書きの発生は、パーソナリティの喪失を生む

©️TOKUSHIMA VORTIS
大学4年生のはじめ、僕は主将という肩書きを得て、制度上の権限のようなものを使えるようになった。
普通に考えれば、それは「できることが増える」ということでしかないが、実際には失ったものも多くあった。そのひとつが、自分のパーソナリティ(人格)だ。
何らかの肩書き、役職を与えれられると、ある種 記号化された状態になる。
つまり、自分が「主将」として話し続ける以上、そのコミュニケーションは「部員」に対してに限られる。主将という立場だから言い、部員という立場だから聞く、ということが常態化してくる。
この変化は、あまり芳しいものではない。記号は記号としか関わることができない。
しかし実際のところ「主将」も「部員」も存在しない。
主将ではなく自分・井筒と、部員ではなくその誰か・佐藤くんなのか鈴木くんなのか、とにかくその人だけがいる。
連絡を超えた何かを伝えるためには、自分が個人的に信じていることを、誰かに個人的に信じてもらう必要がある。
井筒が話し、佐藤くんに共感してもらう以外に方法はない。このプロセスの総合がリーダーシップと呼ばれる。
大勢の前で熱弁をふるう 絵に描いたようなリーダー像は、このプロセスを同時多発的に実現しているに過ぎない。だから、そのスタイルこそリーダーというわけではないし、自分はどういう人間か、チームはどういう組織かに基づいてのみ規定されていくべきではある。
しかし、とにもかくにも、記号化された状態を脱しないことには、個々の最適解としてのリーダー像へ枝分かれしていく、その分岐点にすら立てないのは恐らく間違いない。
部員150人全員と1on1ミーティングを行う
このことに気づいたのは主将になってからずいぶんと経ったあとで、手段を選んでいる余裕はなかったのでローラー作戦を展開することにした。それで思いついたのが、部員全員との1on1ミーティングだ。
正確には、自分とNo.2と部員という三者面談の形をとった。全体に詳しい狙いは伝えず、各自希望する日時を部室前に貼った用紙に書くようにだけ頼む。
30分刻みで、時には朝から晩まで埋まってしまうこともあった。面談の内容には試行錯誤したが、その人それぞれに合わせることを意識すると上手くいくことが多いという印象を持っている。
というのは、基本的に緊張してるので、楽しい話題から振っていくことはマストで、しかし、どこに食いつくのかがみんなバラバラだから難しく、恋愛、オフの日にしていること、サッカーのプレー、何がその人にとっての「楽しい話題」なのかを見極める作業から入る。
だからこそ事前のリサーチも欠かせない。誰と仲が良いのか、試合には出ているのかといったことは当然知っている必要がある。
そういうことをしていると、いかにただ話すことが難しいかということに気づかされる。会話が噛み合わなくなったり、間がもたなくなったりする。
これが、記号化されたもの同士の限界であり、この程度の関係性の中で人を巻き込んでいくなど不可能に決まっている。主将という記号を振りかざすだけのリーダーシップが、往々にして失敗に終わるのにはこういうメカニズムがある、と思う。
まずは、自分を見てもらう

©️TOKUSHIMA VORTIS
きっと全体の前で喋るところしか見たことがない後輩たちに、確かにここに、熱の通った井筒という人間がいて、自分とそう変わらないその人間が 主将をやっていることを知ってもらう。
次に、彼らのことを見る。
こちらからすれば部員150人の中の、150分の1だった存在が、こうして話すことでくっきりと浮かび上がってくる。経歴も、行動も、評判も、そんなものは彼らという人間の、ほんの数%の表象でしかないことを思い知らされる。
二度の日本一を含む、大学サッカー史上最も輝かしい成績を残してから3年が経った。
自分は、その振り返りをするように努めてきた。
ここからは後日談で、述べてきた通り1on1ミーティングの必要性に気づき、実行し、部員との信頼関係が出来上がった先に、求めていた結果があった、というストーリーで成果について語ることも多い。
しかし、必ずしも1on1ミーティングが皆にとって直接的に良いものであったかには疑問が残るのもたしかだ。
「正直、あの1on1ミーティングは地獄でした」
当時の1年生から「今だから言えること」としてもらったフィードバックは意外なものだった。
何を話せばいいのか分からないし、何を評価されているのか分からないし…と。
自分のリーダーとしてのブランディングに問題があったのは重々承知した上で、ある意味歩み寄るように部員向けの打ち手を作っても、それは常に「主将の命令」になってしまうということに結局は自分は気づけていなかった。
聞いたときはショックだったし、リーダーシップというものの魔力の恐ろしさを再確認した。
ただ、部員にとっては意味のない時間だったかもしれないが、主将である自分にとっては価値のある体験だったことにかわりはない。
先に述べた通り、少なくとも自分は、部員を「記号」として見ることをやめることができた、そして、自分の頑張りが彼らの幸せに繋がっているはずだということに、確信を持つことができた。
ピッチ外でもピッチ内でも、当然のようにパフォーマンスが上がった。
これがきっと正しい順序であって、そういうリーダーの姿が、ひとりひとりの部員の心に届き、彼らは自分のことを記号ではない存在として認識してくれるようになるのだろう。
※Top photo : yasuyo KANIE